|
● 感情を押さえ込みすぎたり、爆発させてしまったりしてしまいます。
どのようにすればいいですか?
|
|
- 押さえ込まなくていいところで押さえこんで耐えようとしてしまいます。その為ため込みすぎて変なところで爆発してしまうことになります。感情をため込むのではなく、感じたときに(人を傷つけないようにしながら)こぎざみに出す工夫をしたほうがいいのではないですか。
- 回りにも感情をうまく出している人がいるので、そういう人を観察してみるといいのではないでしょうか。ラクラクとやっているのではなく、苦労しながら体験して身につけたものだということがわかります。私たちは押さえ込むばかりで感情を出す体験が少なすぎます。
- 感じたことを素直に表現して素直に感動しましょう。
- 感情を押さえ込むことは誰でもやることだが無理矢理押さえ込んで身体に支障をきたすようなことはしないほうがよいです。
- なくでも自分一人で全部やろうとすることも大切ですが、あまり一人だけでやろうとしすぎるのはよくありません。自立(きちんと他人にたよれる生活)することが大事です。
|
|
|
----- 森田先生のことば --------------------------
|
<同時に反対の心が起こる>
なお精神の拮抗作用とは、吾人はある感じもしくは欲望が起これば、同時に之に相当して必ず之と
反対の心が起こって、吾人の行動を生活に適応させるようになっている。
人にほめらるれば一寸自ら省みて所謂後ろめたくなったり、人に非難されては、
何となく反発の心の起るのも之が為である。皆精神の適応若しくは保護作用と見ることが出来る。
或は吾人が物を買いたい、酒を飲みたいと思う、もしこゝに精紳の拮抗作用がなく利害得失の考慮、
欲望と抑制との反対観念の葛藤が無かったならば、それは直ちに直接行動となって、濫費者となり
呑んだくれとなるのである。神経質の行動は之と反対に此拮抗作用の強すぎるがために常に抑制的になる。
強迫観念に高所恐怖というものがある。それは例えば絶壁のような高いところの上に立てば、
之から飛び下りて見たいという考えが起る。今にも飛び下りて死ぬるやうな気になって恐ろしくてたまらない。
ガケのある途や総て高いところに行くことが出来ない。これは元もと誰にでもある高いところから
落ちればあぶないという拮抗心の保護作用である。併し普通の人は只そんな心が一寸ひらめくのみで、
神経の流動に従い直ちに流れ去って影を止めない。即ち殆んど自らそんな事を感じないと同様である。
前の、鼻の恐怖の例でも自分の鼻の先の見えない人は鼻なしより外にはない。併し全く之を気に止めないから
見えないと同様である。高所恐怖の患者は飛び下りたらどうしようという恐怖に捕らわれる。
そして鼻尖恐怖の患者のように其恐れに執着して之を常人の心理と知らず、自ら病的に起こることと
独断してますますその考えが発展し終には高いところへ行けば直ちに飛び下りるかのように思い込んで
しまうのである。之は意志薄弱やヒステリーには何かの機会にこんな事が無いとは限らないが強迫観念
には如何なる場合にも決してそんな事はない。何となれば何処までも心の葛藤の内に終始して決して
行為の前提たる決意というところに達することがないからである。
又自分がフイと心の調子が狂って自分の赤ん坊を踏み殺す事はないかという恐怖や、
自分の妹を空気銃でうつような事があっては大変との恐怖や高貴の人や神仏を冒涜する事の
恐怖等皆そうあってはならぬという拮抗心から起る事で、普通の人は其ままに思い流して行
くけれども、強迫観念は之を恐怖する為に余のいわゆる精神交互作用によってますます之に執着するようになる。
又自分が窃盗するに非ずやとの恐怖や自分が不徳義をして人に排斥さるるに非ずやとの恐怖など皆自己保存に対する
精神の拮抗作用から起こるものである。一般に良心と名づくるものは、その社会の以て善と見作すことをして心に
満足を得、悪と名づくる事をすることを恐れるという精神の拮抗作用である。世の人はこの精神葛藤からしばしば
誤りたる善悪観に陥ることがある、皆思想の矛盾から起こるのである。(森田正馬全集 第2巻 P.133〜134)
<主義や理論がなければ直情のままになる>
君がいわれたように、僕が悲しい時に慟哭して、まもなく後で、ケロリとしているという事は、
いろいろの理由もありましょうが、その最も大きな条件は、年とって図々しくなるという事かも知れません。
小児か無邪気であるから、泣くも笑うも変わりやすい。その外聞を構わないという点においては、
小児と老人と同様である。その違う点は、老人は酸いも甘いも、多くの経験を積んでいるから、
その感情が微細にわたるという事であります。
これに反して若い人、心掛けのよい人、道学者あるいは武士道とかいうものでは、男は泣いてはならぬとか、
人に対して失礼である、みっともないとか、あるいは諸行無常と悟ったとか、おのおのその主義や理論や
片意地やで、感情を抑えているのであるが、私にはその様な主義や理論がないから、感情のままに小児のようになる。
それでもさすがに告別式とか、多数の人の前では神妙にしているが、それは自然にきまりが悪いからであって、
心安い人ばかりの時は、耐えきれないで泣くのである。そういう風であるから、泣いてしまえば感情が放電されて、心が晴れてなんともなくなるのである。
これを私の妻と比較すると、妻の方にはいろいの理屈がある。
どうすればこの悲しみに堪えられるか、これから先どうして生きて行かれるかとか考え、
あるいはあきらめる事についても、さまざま工夫をする。
僕の方でいえば、死は当然悲しい。どうすることもできない、絶対であって比較はない。
七歳の子を失うも、二十歳の子を死なすも、変死でも、長い間の病死でも、いずれもその親の心にとっては、
全的の絶対の悲しみである。人に憎まれる悪い子は、それがかわいそうで悲しく、人に誉めらるる良い子は、
その事が惜しくて悲しい。「もろともに苔の下には朽ちずして、埋もれぬ名をきくぞ悲しき」。
またこの悲しみを、どうにもあきらめうべきはずのものではない。ただしかしながら一定の時日を経る間に、
悲しむままに悲しみがなくなり、あきらめないままに、自然にあきらまるのである。
私もかねての想像では、子供が亡くなれば、自分は身も心も取り乱して、とても生きてはいられぬか
と思ったけれども、実際にぶつかってみれば、やはりなるようになって、このままに生きて行かれ、
こんな事も話する事ができるようになるのである。
(森田正馬全集第5巻 P.68〜69)
|
|
|
|
|
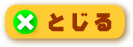
|

